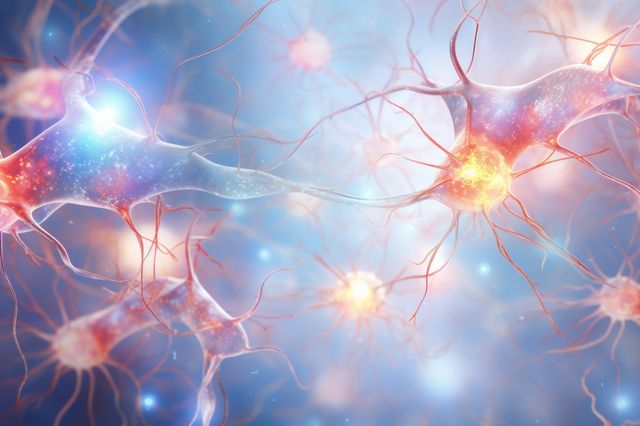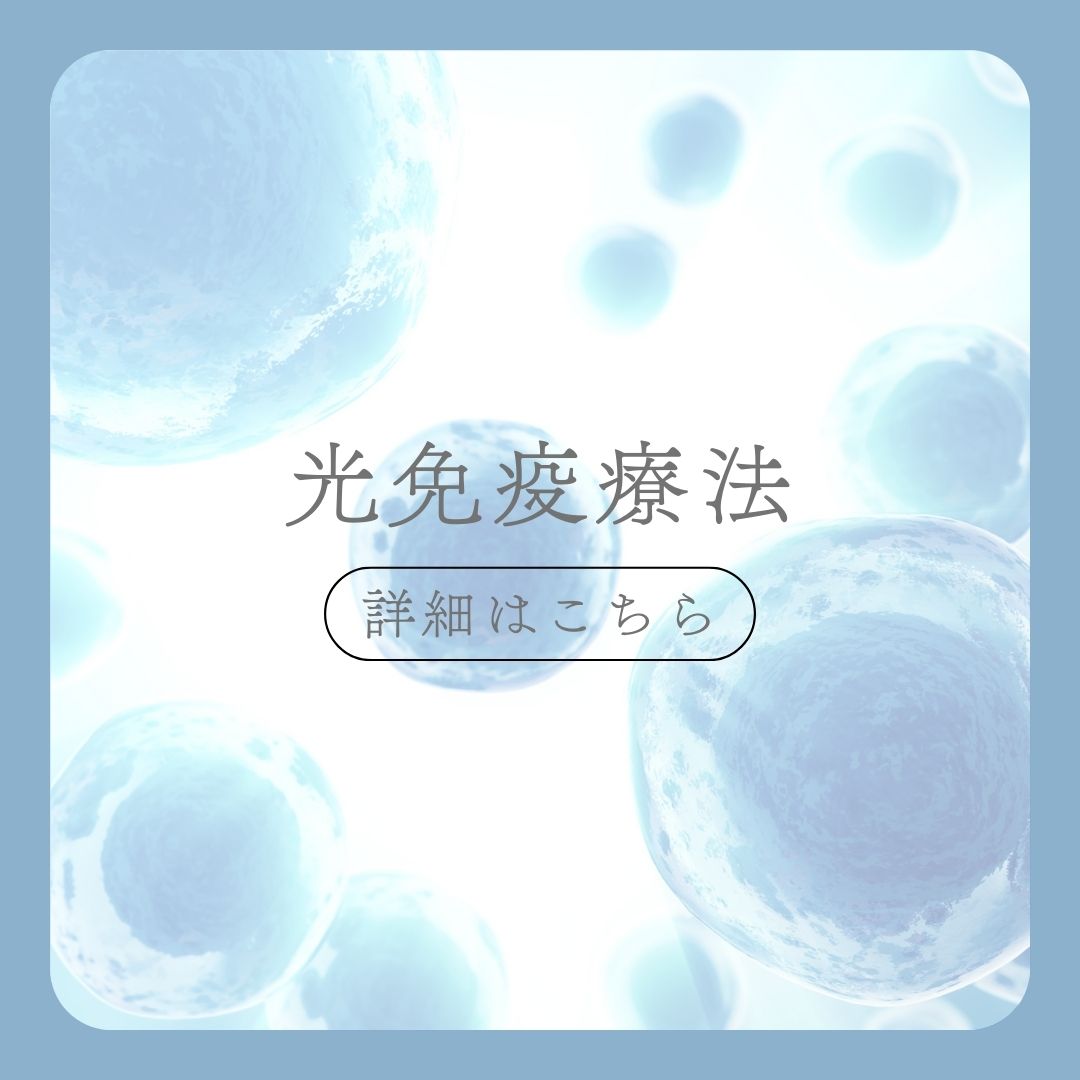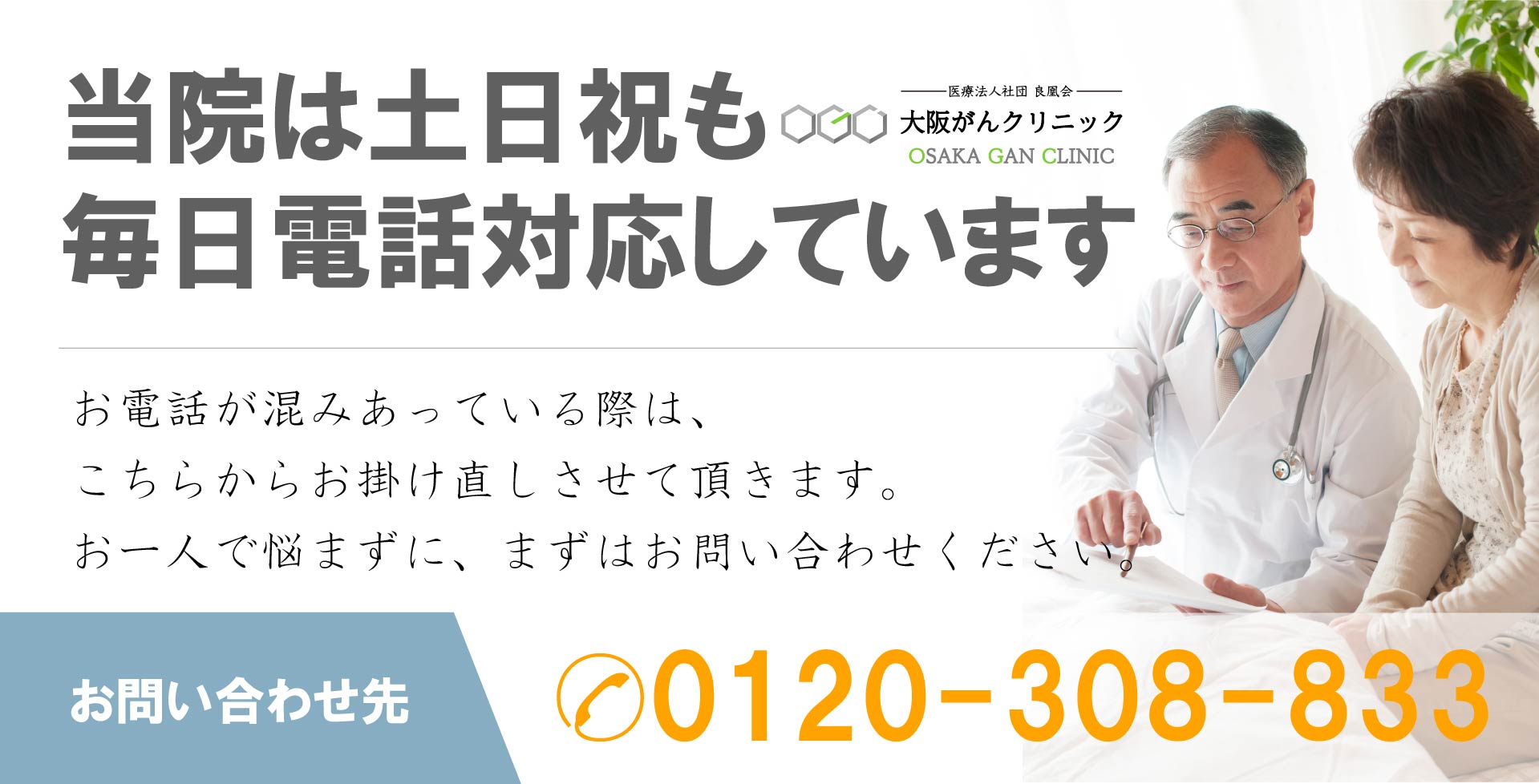卵巣がんとは
卵巣には多種多様の腫瘍が発生し、卵巣がんはその中でも悪性腫瘍のことを指します。
また、腫瘍ができる場所によって、上皮性腫瘍、性索間質性腫瘍、胚細胞腫瘍などに分類されます。
最も多く発生するのが上皮性腫瘍であり、卵巣がんのうち約90%がこのタイプとなります。
そのため、一般に「卵巣がん」といえば、上皮性の悪性腫瘍のことをいいます。
初期段階では自覚症状がほとんどないため、早期発見が困難という特徴もあります。
この記事では、70代の卵巣がんに関する情報をお伝えします。
70代の卵巣がん罹患率
年代別にみた卵巣がんの罹患率は、40歳代から増加し、50~60歳代がピークとなります。
そこから徐々に罹患率が下がっていきますが、70代でも高い数値となっています。
具体的には、人口10万人に対し、70~74歳で約28人、75~79歳で約24人と2020年の「全国がん登録罹患データ」によって発表されています。
日本においては、卵巣がんは増加傾向にありますので、この数値も少しずつ増えていくことが予想されます。
70代の卵巣がんの死亡率
卵巣がんの死亡率は、50歳以降増加していき85歳以上がピークとなります。
70代の卵巣がんの死亡率は、人口10万人に対し、70~74歳で約15人、75~79歳で約15人と2020年の「全国がん登録罹患データ」によって発表されています。
医学の進歩により、死亡率は年々少しずつ減少してきていますが、生活習慣の変化や高齢化などによって卵巣がんの罹患者は増えています。
そのため、死亡者数も少しずつ増加傾向となっています。
70代の卵巣がんの症状
卵巣がんは、サイレントキャンサーとも呼ばれ、自覚症状がほとんどないタイプのがんです。
卵巣がんがステージⅣの末期状態まで進行したとしても、膀胱を圧迫して頻尿になったり、腹部の圧迫感やウエストがきつくなったと感じたりする程度で、卵巣がん特有の症状が出ることは稀です。
また、卵巣がんは年代によって症状が出やすいといったこともないため、70代で卵巣がんを発症した場合でも、進行した状態で発見されることが多いです。
そのため、上記のような症状が継続する場合、医療機関で検査を受けるようにしてください。
70代の卵巣がんの診断
70代であっても、卵巣がんの診断は、超音波検査やMRI、CTスキャン、腫瘍マーカー検査などを用いて行われます。
これらの検査により、がんの位置や拡がりなどを評価します。
そして、初回手術による病理検査によって、進行度や組織型などを確定診断します。
70代の卵巣がんの治療
卵巣がんの治療は、がんの種類や進行度、患者様の全体的な健康状態によって異なります。
一般的には、70代の卵巣がん患者様に対しても、手術と化学療法が主な治療法となります。
しかし、高齢者への手術は、合併症の増加、心肺機能の低下から周術期合併症が増加するため、注意が必要となります。
卵巣がんの手術後、30日以内の死亡率は、70歳未満で約1.5%であるのに対し、70〜79歳では6.6%と上昇します。
基本術式だけでなく、腸管部分切除術、横隔膜切除術、脾臓摘出術など、手術の複雑性が増すに連れて周術期合併症も増加するため、術後管理が重要となります。
光免疫療法と卵巣がん
光免疫療法は、特定の光を用いてがん細胞を選択的に攻撃する治療法です。
この方法は、がん細胞を選択的に攻撃しつつ、正常な細胞へのダメージを抑えることができるため、副作用が少ない点が利点の一つです。
70代の卵巣がん患者様は、体力の低下や合併症などによって、標準治療を継続するのが難しい場合があります。
そのような場合でも、光免疫療法であれば適用できる可能性がありますので、卵巣がん治療にお悩みの方は一度ご相談ください。
以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。
まとめ
70代の卵巣がんは、罹患率はピークから少し下がっているが死亡率は高い数値となっている。
診断方法や治療は年代によって大きな違いは無いが、手術による合併症などのリスクが増加するため、術後管理が重要となります。
卵巣がん治療には、手術や化学療法といった標準治療の他に、光免疫療法という選択肢も存在します。
光免疫療法は副作用が少ないという利点があるため、体力や免疫力が低下している高齢者でも適用できる可能性があります。
適した治療の組み合わせにより、より良い治療成績を残せるようにすることが望まれます。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧