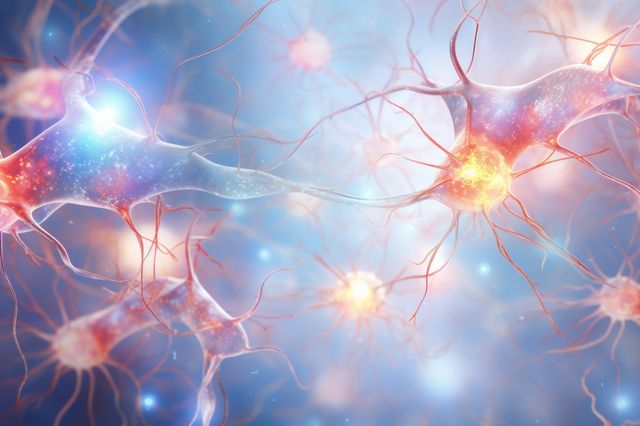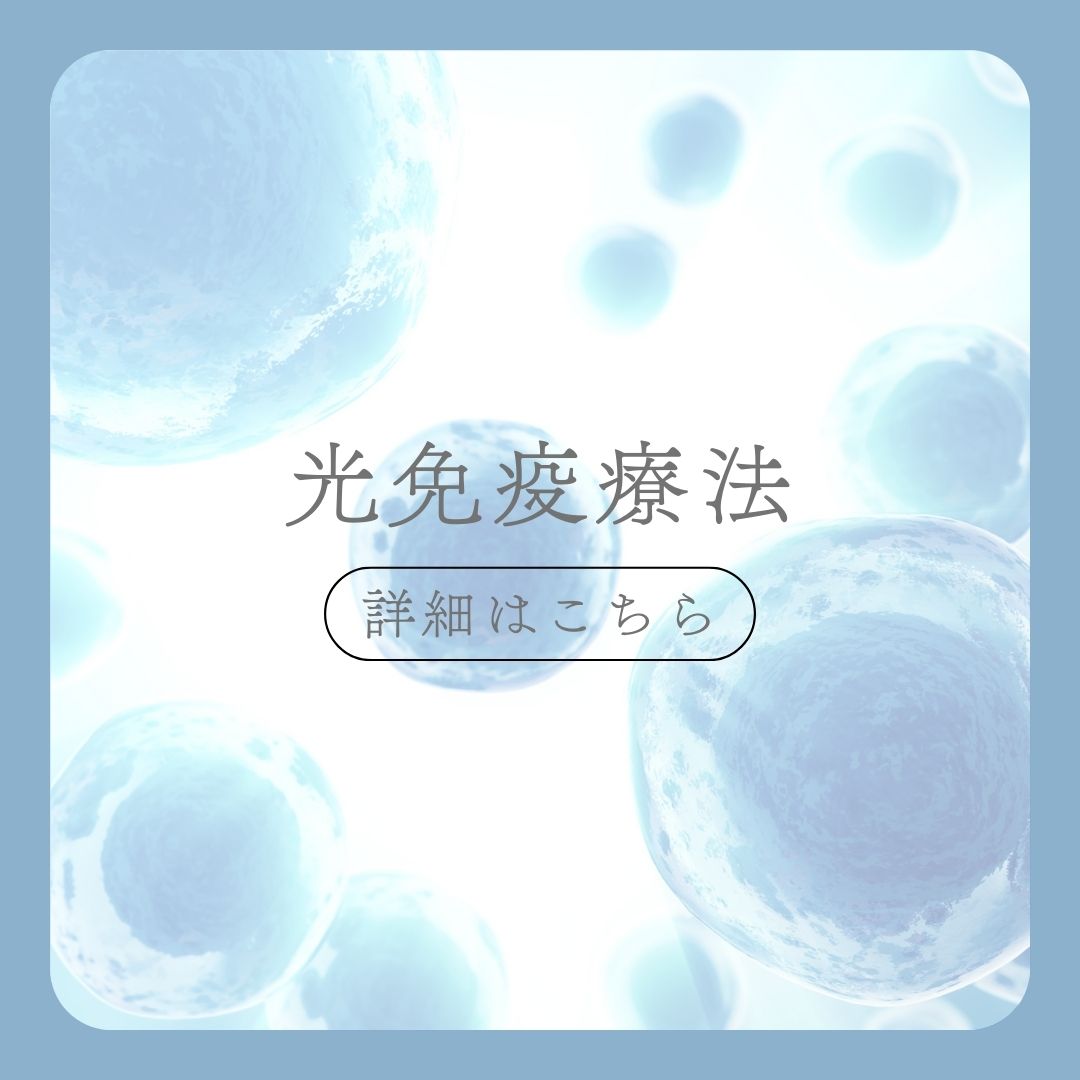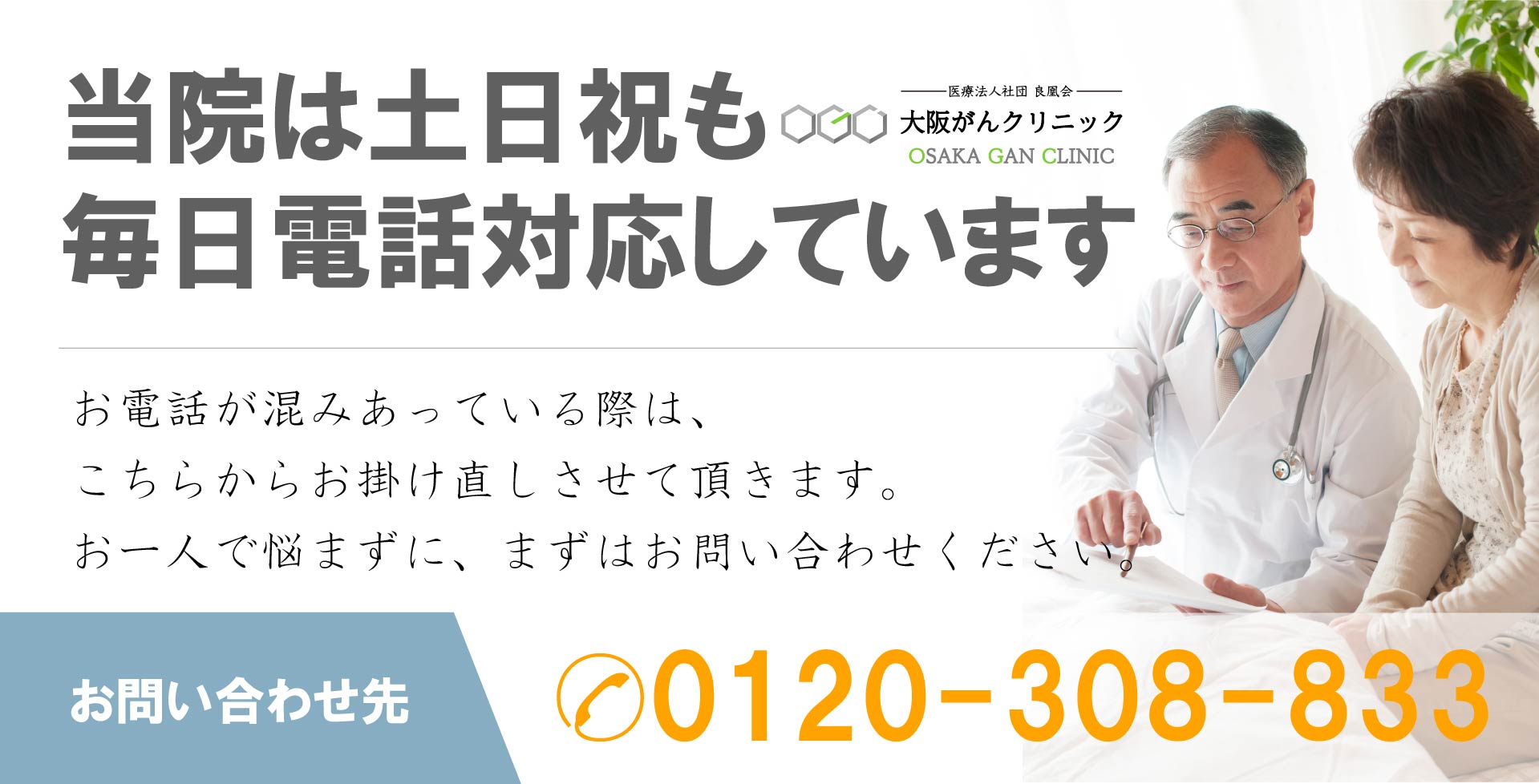卵巣がんと化学療法の基本的理解
卵巣がんとは
卵巣がんとは、卵巣を構成する組織に発生する悪性腫瘍の総称です。
卵巣がんはサイレントキャンサーとも呼ばれ、自覚症状に乏しいことが多く、無症状のうちに進行してしまい診断時には約半数が進行がんの状態で発見されるといわれています。
また、卵巣がんが発症する年代は、40歳前後から増え始め60代がピークとなります。
そして、卵巣がんは発生起源によって、上皮性腫瘍、胚細胞腫瘍、性索間質性腫瘍の3種類に分けられ、全体の約90%が上皮性腫瘍となります。
さらに、上皮性腫瘍は漿液性がん、明細胞がん、類内膜がん、粘液性がんなどの組織型に分類され、組織型によって化学療法の効きやすさなどに違いがあります。
卵巣がんに対する化学療法
卵巣がんは、がんの中でも比較的に化学療法が良く効くがんといわれています。
化学療法は、抗がん剤や分子標的治療薬を用いて、体内のがん細胞の増殖抑制を目的に全身療法として行われます。
手術後の補助療法以外にも、手術前に腫瘍の縮小化を図るためや、がんが腹腔内に拡がっている場合にも適用されることがあります。
化学療法を行う時期
卵巣がんに対する化学療法は、目的と行われる時期によって、主に初回化学療法、術前化学療法、維持化学療法、二次化学療法があります。
●初回化学療法
基本的には、初回手術後に術後化学療法として行われます。
初回化学療法の基本となる薬剤は、タキサン製剤とプラチナ製剤で、この2つを併用する治療法は「TC療法」と呼ばれます。
●術前化学療法
術前化学療法は、手術による根治率向上を目的として、手術前に行わ舛。
初回手術によって腫瘍を取り切れないと予測される患者様や、健康状態や合併症などによって手術を行えない患者様が適用対象となります。
●維持化学療法
維持療法とも呼ばれ、初回手術や化学療法による治療後に行います。
がんの再発や増殖を防止することを目的とし、血管新生阻害薬とPARP阻害薬といった分子標的治療薬を用います。
●二次化学療法
がんの再発時や初回化学療法に対して抵抗性を示した場合に行われる化学療法となります。
プラチナ製剤による治療終了後から再発までの期間が6ヵ月以上経過している場合は、プラチナ製剤に対する感受性が高いとされ、6ヵ月未満の場合は、プラチナ製剤抵抗性と判断されます。
プラチナ製剤感受性の再発ではプラチナ製剤を含む多剤併用療法が選択され、プラチナ製剤抵抗性の再発では前治療と異なる単剤治療が推奨されます。
化学療法の副作用と管理
化学療法(TC療法)によって引き起こされる代表的な副作用として、嘔気・嘔吐、浮腫み、筋肉痛、関節痛、白血球・血小板減少、発熱性好中球減少症(FN)、末梢神経障害、脱毛などが挙げられます。
また、アレルギー反応、嘔気・嘔吐などは急に起こる副作用となります。
アレルギー反応が強く出ると命に関わる可能性もあるため、十分な管理体制と、アレルギー反応が出たときの対応を素早く行うことが重要となります。
遅れて起こる副作用としては、筋肉痛・関節痛、むくみ、末梢神経障害、脱毛などがあります。
副作用の対策として、血液毒性を早く改善する薬や吐き気を抑える薬などを使用して、症状の緩和に努めます。
光免疫療法の概要と卵巣がん治療への応用
光免疫療法は、特定の波長の光を用いてがん細胞を標的とする治療法で、卵巣がん治療においてもその利用が期待されています。
副作用の少ない治療法のため、年齢的に手術や化学療法が難しい患者様に対しても適用できる可能性があります。
以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。
化学療法と光免疫療法の組み合わせ
卵巣がん治療において、化学療法と光免疫療法を組み合わせることで、相乗効果が期待できます。
特に、化学療法に耐性を持つがん細胞に対しても、光免疫療法が治療の選択肢となり得る可能性もあります。
標準治療だけでは卵巣がんに対して満足のいく治療効果を出せていない患者様は、光免疫療法もご検討ください。
まとめ
卵巣がんの治療法は、手術と化学療法の組み合わせが基本となります。
比較的に卵巣がんは化学療法が効きやすいがんのため、化学療法は積極的に行われます。
化学療法を行う時期は、手術前、手術後、初回治療後の維持療法、再発時の二次化学療法があります。
強い副作用が出る可能性があるため、化学療法後の観察や管理体制の構築が重要となります。
光免疫療法は、手術や化学療法などの標準治療と組み合わせることで、相乗効果を期待できます。
卵巣がんに対しても適用可能な場合がありますので、標準治療だけでは満足のいく結果が出ていない方は一度ご検討ください。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧