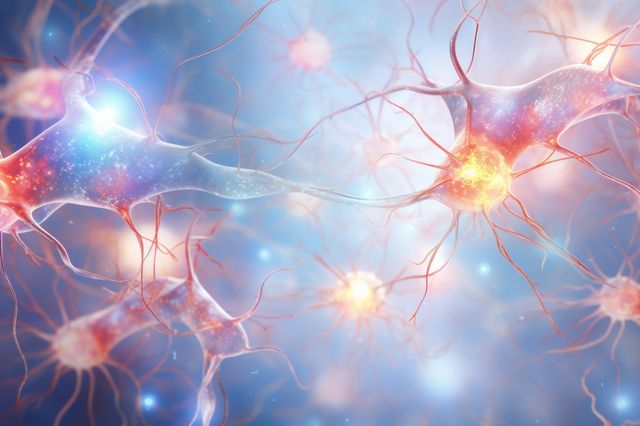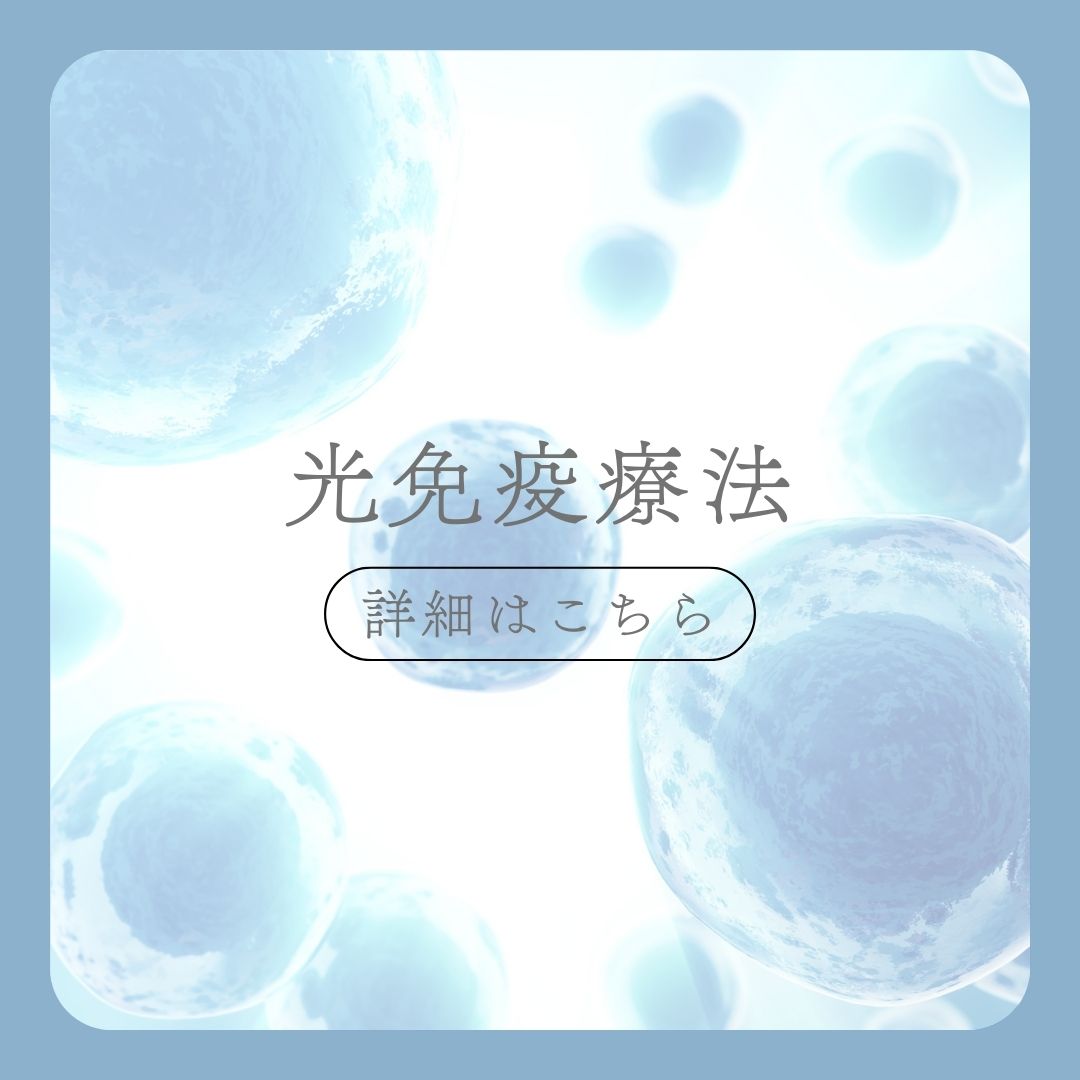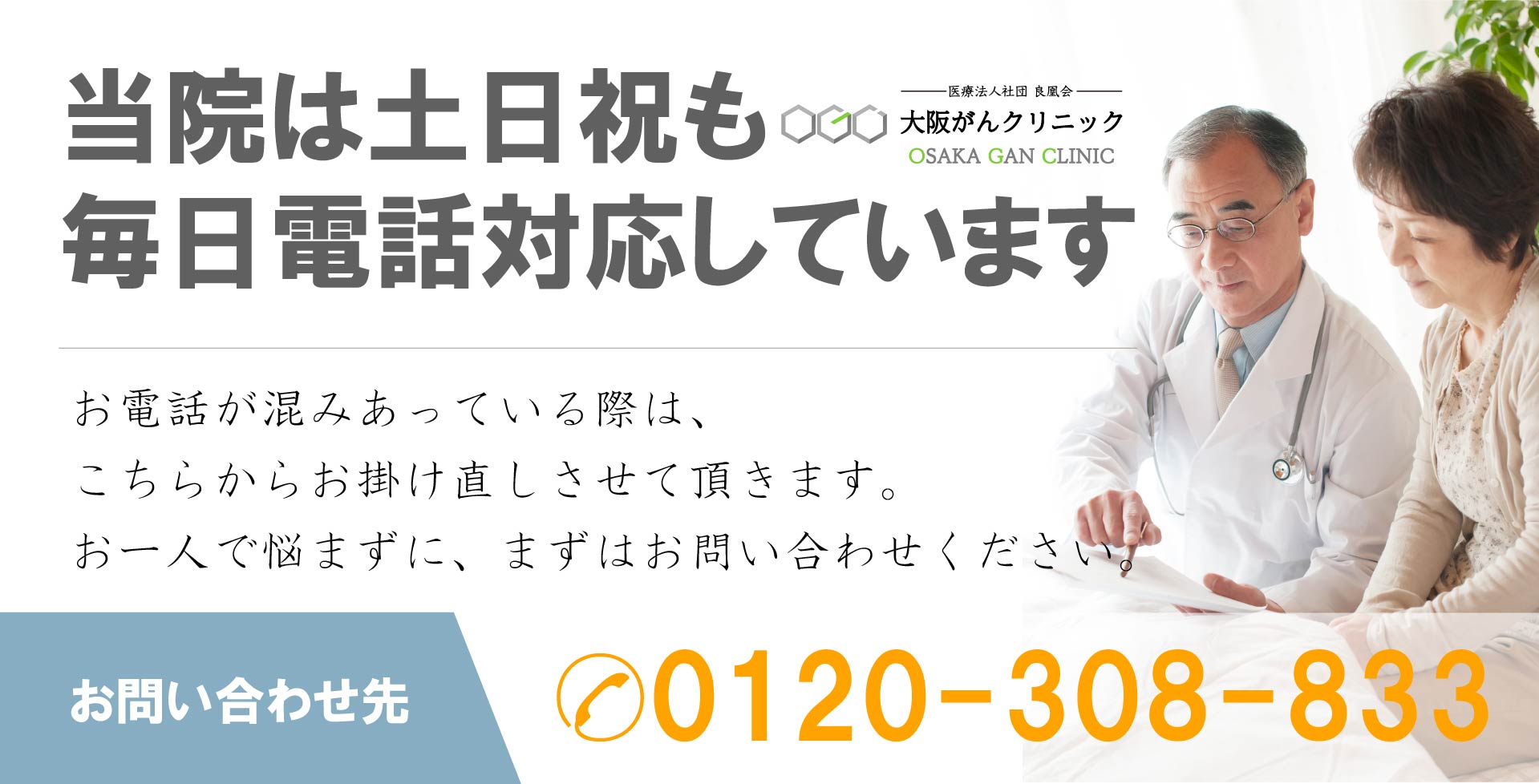卵巣がんの進行と診断
卵巣がんは、子宮の左右にある卵巣から発生するがんです。
40歳前後から罹患者数が増え始め、50代~60代前半が発症のピークとなります。
また、HBOCという遺伝的要因で卵巣がんを発症する人は、卵巣がん患者全体の約10~15%を占めています。
このがんは初期段階で自覚症状がほとんどなく、半数以上が進行してから発見されています。
症状が現れた時には、がんはすでに進行しており、根治が困難な状態になっていることも少なくありません。
卵巣がんの分類
卵巣がんは発生する部位により、上皮性腫瘍、胚細胞性腫瘍、性索間質性腫瘍に分類されます。
上皮性腫瘍が最も一般的であり、卵巣がん患者様の約90%を占めています。
さらに、これらのがんは、診断によってステージⅠ~Ⅳの進行度、漿液性がん、類内膜がん、明細胞がん、粘液性がんという4つの組織型に判定されます。
ステージと組織型によってその後の治療法が決定されるため、これらの診断は重要となります。
診断とステージ
卵巣がんの診断には、超音波検査、CTスキャン、MRI、血液検査(CA-125などの腫瘍マーカー)、そして手術による病理診断が行われます。
がんのステージは、Ⅰ期~Ⅳ期に大きく分類され、半数以上がステージⅢ~Ⅳの進行がんとなります。
卵巣がんは自覚症状に乏しく、腹部の痛みなどで婦人科を受診した際に、卵巣がんが見つかることが多いです。
卵巣がんの治療
卵巣がんの主な治療法は、手術と化学療法ですが、がんの種類、進行度、患者様の一般的な健康状態に基づいて慎重に決定されます。
ステージⅠ~Ⅱでは、がんの完全摘出を目的とした、基本術式と呼ばれる手術を行います。
手術では、卵巣と卵管、子宮、大網を摘出し、周囲のリンパ節も取り除きます。
また、手術後は再発リスクを低減させるために、化学療法が行われます。
しかし、卵巣内のがんを完全に摘出し、悪性度が低いと判定された場合には、術後の化学療法は行わず経過観察となります。
ステージⅢ~Ⅳも治療の流れは同様ですが、腫瘍縮小を目的として手術前に化学療法を行うことがあります。
高齢者や合併症のある方、全身状態が悪い方に対しては、手術を行わず化学療法のみで治療するケースもあります。
進行した卵巣がんの場合、これらの標準的な治療法だけでは十分な効果が得られないことがあります。
再発しやすい卵巣がん
卵巣がんは、初回治療によって画像診断でがんが無くなったとしても、半数以上の症例で再発が起こります。
再発は、同じ場所にがんが発生するだけでなく、リンパ節転移、肝臓や肺といった他の部位へ遠隔転移することもあります。
再発するまでの期間は、初回治療終了後から2年以内のことが多く、ステージⅢやⅣの進行がんでは、2年以内の再発転移が約55%、5年以内の再発転移が70%以上と高い数値となっています。
再発転移した場合、治療の目的は根治を目指すことから、進行を遅らせることや症状の緩和に変わります。
また、再発後の生存期間の中央値は約2年と短く、再発後の根治は困難であることから、予後は悪いことが分かります。
光免疫療法とは
光免疫療法は、特定の波長の光を用いて活性酸素を生成し、がん細胞を破壊する治療法です。
この方法は、患者様の体内で直接がん細胞を標的とするため、周囲の正常な細胞への影響を抑えることができます。
以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。
光免疫療法の利点
光免疫療法の利点は、その選択性にあります。
がん細胞のみを標的とすることで、患者様の体への負担を軽減することができます。
また、従来の治療法に抵抗性を示すがん細胞に対しても適応できる可能性があります。
光免疫療法は、進行した卵巣がんや再発転移した卵巣がんに対しても、有効な治療法となる可能性があります。
手遅れと判断され、根治を目指す治療から症状の緩和を目指す支持療法となった患者様でも一度ご相談ください。
まとめ
卵巣がんは、自覚症状がほとんどなく、発見時には半数以上が進行がんとなっている。
ステージⅢ・Ⅳの進行がんでは、手術と化学療法が主な治療法となるが、標準治療だけでは完治が目指せないことも多い。
再発転移をしやすいがんであり、進行がんでは2年以内に50%以上、5年以内に70%以上が再発する。
再発した場合、根治を目指すことは難しく生存期間の中央値も短いため、予後は悪い傾向にある。
光免疫療法は、進行した卵巣がんに対しても適応できる可能性がある。
標準治療と組み合わせることも可能なため、標準治療だけでは根治が難しかった患者様に、より良い治療成績を期待できます。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧