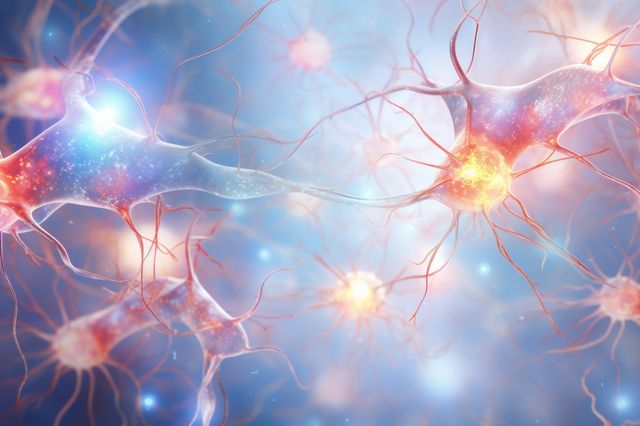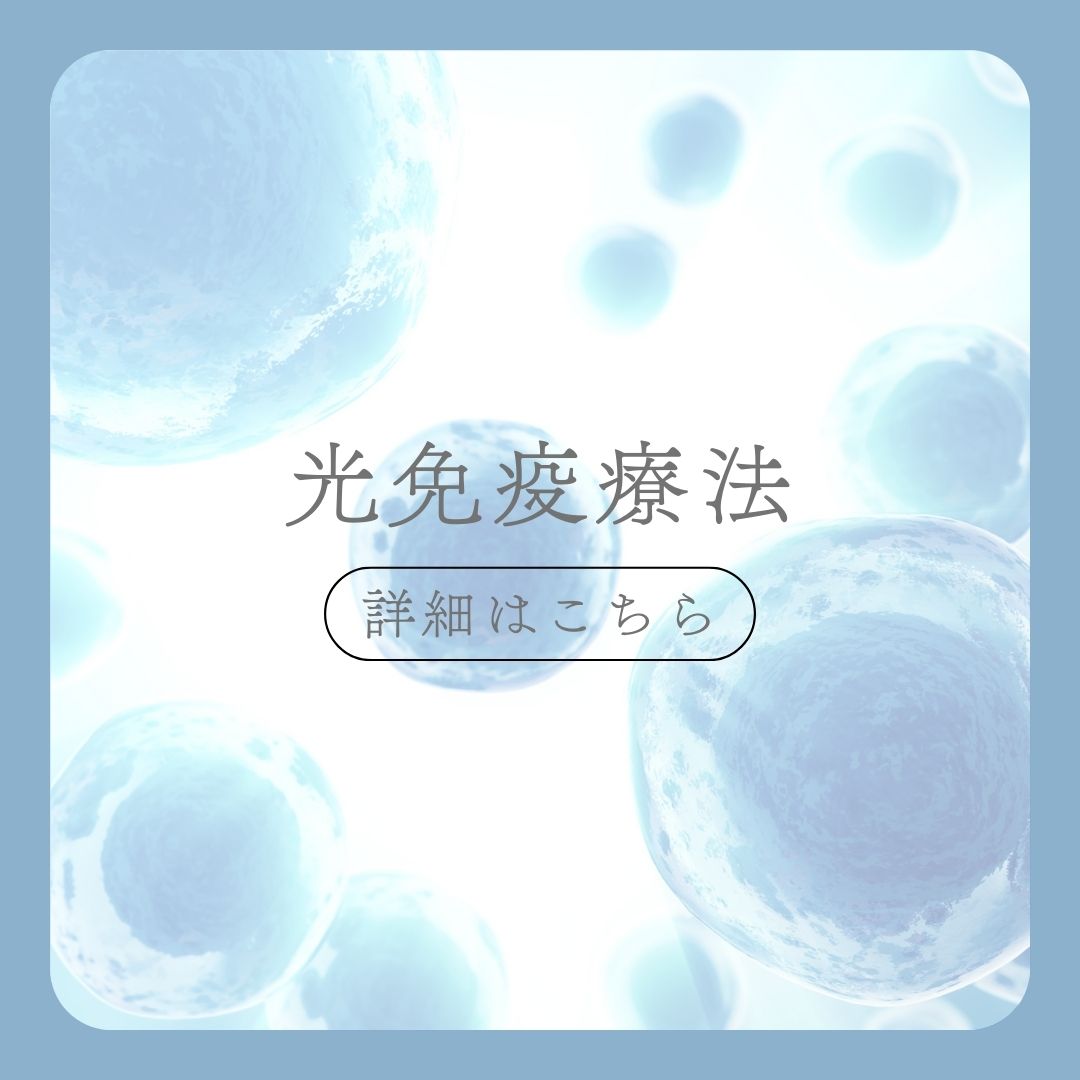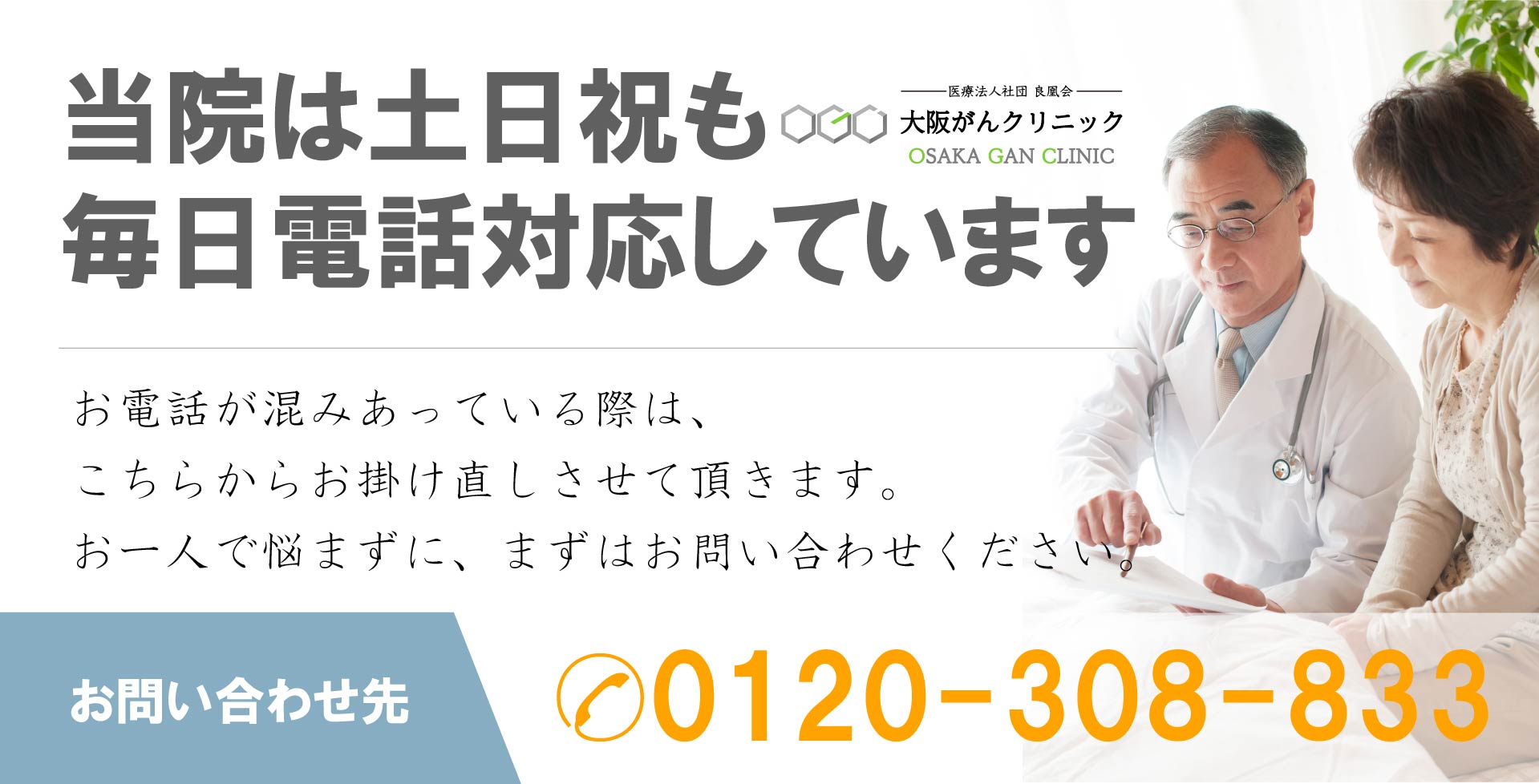膵臓がんの再発転移と光免疫療法の詳細解説
膵臓がんの概要と再発転移の背景
膵臓がんは、主に腺管細胞がん(約90~95%)から発生する悪性腫瘍で、診断時の約70~80%が進行期(ステージⅢ~Ⅳ)であり、5年生存率は約5~9%と極めて予後不良です。
日本では年間約45,000人が新たに診断され、死亡数は約40,000人(2023年統計)です。
再発転移とは、根治手術(膵頭十二指腸切除術など)や化学療法後に、残存がん細胞が再活性化し、局所再発または遠隔転移を起こす状態を指します。
切除例の約70~80%が2年以内に再発し、非切除例ではほぼ100%が進行・転移します。
再発リスクが高い理由は、膵臓の解剖学的特徴(後腹膜臓器、豊富な血管・リンパ網)と、がん細胞の浸潤性(KRAS変異90%以上による)にあります。
微小転移(ミクロメタスタシス)が初診時から存在し、手術や化学療法で完全除去が困難なためです。
再発転移の種類と頻度
再発転移は局所再発と遠隔転移に分類され、以下のように多発します。
●局所再発(約30~40%):膵切除断端、腹腔内リンパ節、門脈周囲に発生。CTで腫瘤影やCA19-9上昇で発見。
●遠隔転移(約60~70%):肝臓(50~70%)、腹膜(40~50%)、肺(20~30%)、骨(10~15%)が主。肝転移は門脈経由、腹膜播種は腹腔内散布による。
切除後再発の中央期間は約8~12ヶ月で、術後補助化学療法でも再発率50%以上とされています。
再発転移のメカニズムと原因
再発転移の主因は微小残存病変(MRD)となります。
手術で肉眼的に切除しても、分子レベルでがん細胞が残存し、増殖・転移を再開します。
●分子メカニズム:
・KRAS変異:細胞増殖シグナルを恒常活性化。
・SMAD4変異:TGF-β経路障害→転移促進。
・間質反応(desmoplastic reaction):薬剤浸透を阻害し、耐性獲得。
●リスク要因:
・腫瘍径>2cm、リンパ節転移陽性、脈管侵襲、CA19-9高値(>500 U/mL)。
・術後補助療法未実施や中断。
画像診断(CT/MRI/PET-CT)と腫瘍マーカー(CA19-9)で3~6ヶ月ごとの定期フォローが推奨されます。
再発転移の症状と診断
再発転移の症状は転移部位により異なります。
●肝転移:黄疸、腹部膨満、肝機能障害。
●腹膜播種:悪性腹水、腸閉塞、腹痛。
●肺転移:呼吸困難、胸水、咳。
●骨転移:骨痛(特に腰椎)、病的骨折。
診断は造影CTで新病変確認、CA19-9上昇(2倍以上)で疑い、生検で確定。
PS(パフォーマンスステータス)評価が治療選択の鍵となります。
再発転移の標準治療と限界
●第一選択は全身化学療法:
・FOLFIRINOX(PS 0-1):mOS約11ヶ月。
・ゲムシタビン+ナブパクリタキセル:mOS約8~9ヶ月。
局所再発には放射線療法(SBRT)や手術(再切除、限定的)が検討される。
分子標的薬(BRCA変異→オラパニブ)は約5%に有効です。
●標準治療の限界:薬剤耐性、副作用(骨髄抑制、末梢神経障害)、QOL低下。支持療法(疼痛管理、栄養サポート)が不可欠となる。
光免疫療法:再発転移への新たな選択肢
当院の光免疫療法は、自由診療として再発転移膵臓がんに対応しています。
ICGリポソームを点滴投与し、EPR効果でがん細胞に集積後、近赤外線レーザーで照射します。
活性酸素でアポトーシス誘導、免疫刺激で転移巣にも効果があります。
標準治療との併用・再発転移への適用によって、腫瘍縮小が期待できます。
以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。
治療選択の考慮点と多職種連携
治療選択は再発部位、PS、遺伝子変異、患者希望で個別化されます。
セカンドオピニオンも推奨され、緩和ケアチームで疼痛・栄養・心理ケアの提供が必要となります。
まとめと今後の展望
膵臓がんの再発転移は切除例の70~80%に発生し、肝・腹膜・肺が主な転移先となります。
化学療法が中心となりますが標準治療には限界も存在します。
当院の光免疫療法は、免疫活性化によって転移抑制・QOL向上の可能性があります。
膵臓がんに関するお悩みは、些細なことでもお気軽にご相談ください。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧