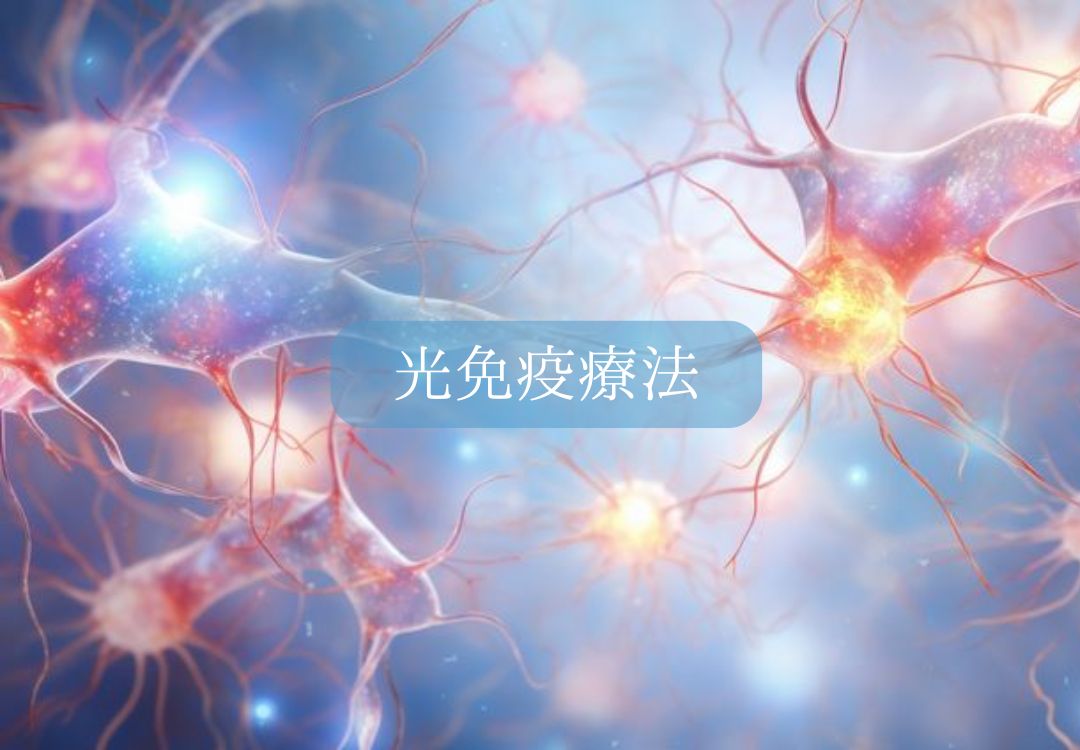がんの進行の仕組みについて(再発、転移とは)
①がんとは
正常な細胞は、基本的に身体やその周囲の状態に応じて、増殖を止めたり、分化して様々な機能を担うようになったり、脱落して他の細胞と入れ替わるような仕組みで、正常な細胞が働いています。
正常な細胞に対して、がん細胞は、こうした仕組みにエラーが生じてしまうことで、時間をかけて増殖し続けたり、他の部位に移りやすくなるといった性質を有しています。
がんの進行については、がんのある部位(位置)やがん細胞の大きさ以外に、患者様の容態(コンディション)、これまでに受けた治療の内容やその治療でどのぐらい効果があったか、そのがんの特徴等、いろいろな要因があります。
がんついて知っておきたい事の詳細をまとめておりますので、より詳細情報をご希望の方はこちら
ここで、再発と転移について、理解を深めて頂くために、大まかなメカニズムについて説明させて頂きます。
まず、一般的に最初にできたがんの部位は「原発巣」と呼ばれます。
例えば、最初に大腸にがん細胞が発生し、ここから肺に転移した状態は肺がんとは呼ばれず、「大腸がんの肺転移(原発は大腸がんであり、大腸から肺転移を起こした状態)」です。
このとき、肺に生じたがんは、大腸がんの細胞と同じ性質を有しているので、転移先のがんは、元々のがんと同じ性質を有することになります。
それ故、大腸が「原発」のがんの場合であれば、肺に転移した腫瘍も、大腸がんに効く抗がん剤でないと反応しません。
初めてがんと診断された場合、病気が進んだ状態で発見されたならば、診断された時点でこれらのがんの状態を幾つか併せ持っていることもあります。
『原発』がどこなのか、その腫瘍は『転移』なのか『原発』なのか、『再発』した部位はどこなのかといった情報はがん治療の方針を決めるにあたって非常に重要です。
②再発とは
がんにおける『再発』とは、がんの治療が順調にいったようにみえて、実際は手術等の治療で完全に除去することが困難なぐらい目には見えない小さながん(悪性腫瘍)が残ってしまっていて、残っていたがん細胞が時間をかけて再び現れたり、化学療法(抗がん剤を用いた治療等)や放射線治療によって、いちど縮小したがんが再び大きくなってしまったり、別の場所に同じがんが出現することを指します。
・抗がん剤の副作用に関してはこちら
また、血液やリンパのがん、前立腺がん等の場合、『再発』は『再燃』という言葉で呼ばれます。
初回の治療で、もしがん細胞が完全に除去できていれば、再発することは勿論ありません。
ところが、実際には、がん細胞が発見されたときには、既に、目に見える転移(この転移がみられるケースとして多いです。)、又は目に見えない転移(微少転移)があるとされています。
その為、初回の治療では、再発や転移を防ぐという目的で、抗がん剤が使われることが多く、再発というのは、決して珍しいことではないのです。
また、がんが再発した場合、以下のような種類の再発状況に分かれます。また、再発の状況によって治療法も異なってきます。
局所再発:原発巣と同じ場所又はごく近くに現れます。
領域再発:腫瘍が最初のがんの発生場所(原発巣)の近くのリンパ節或いは組織で成長したときに現れます。
遠隔(全身)再発:最初のがんの発生場所(原発巣)から離れている器官若しくは組織に転移しています。
がんの再発はどれくらいあるかをステージ毎に5年生存率を基に、具体的に見ていきましょう。
・5年生存率を先に確認する場合はこちらをクリック
③転移とは
治療した部位付近で再発を指摘されること以外に、別の部位に『転移』としてがんが発見されることも再発に含まれます。
『転移』とは、がん細胞が最初に発生した組織(原発巣)から、血管やリンパへ入り込み、血液やリンパの流れにのることで、別の臓器や器官に移動し、そこでがん細胞が増殖することを指します。
重複してしまいますが、がんの仕組みをベースに、もう一度『転移』について少し細かくみていきましょう。
本来、人間の身体を構成する無数の細胞は、各々の臓器や組織に固定されており、細胞は元々の場所を離れて、体内を勝手に移動することはありません。(但し、例外として、赤血球、白血球等の血球が挙げられます。)
これは細胞同士がお互いにしっかり結びついているからです。(化学の分子間の結合のイメージして頂けると分かりやすいかもしれません。)
これは良性腫瘍にも適用されており、良性腫瘍もまた、人体の組織を構成する細胞が、自分の持ち場を離れてしまえば、直ぐに消滅してしまいます。
ところが、がん細胞(悪性腫瘍)は、上記のルールに従わず、組織を離れても、生き続けることが可能で、血球やリンパ液に混じって他の臓器や器官へ移り、そこで再度、増殖し始めてしまいます。これが『がんの転移』です。
上記のように述べましたが、実際には、全てのがん細胞が転移を引き起こすという訳では有りません。
血管やリンパ管に侵入したがん細胞の内、長い間生き延びて、別の部位で増殖可能になるがん細胞は、全体のうち、0.1%程度であり、これは細胞に換算すると1000個に1個程度に相当します。
しかし、血液中に侵入するがん細胞の数は途轍もない数なので、決して小さな数値とはいえません。
がん細胞がもとの場所から遠く離れたところに転移(遠隔転移)するまでには、次のような変化を起こしていると見られています。
1)周囲の組織との結びつきを失ってはがれやすい状態になる。
2)運動能力を得て、組織内でふらふらと動き出す。
3)血管を成長させる物質を放出して新しい毛細血管をつくり出し、それをがんの近くまで引き寄せる。
4)血管の壁を溶かす物質を出して血管内に入り込む。
5)血流に乗って他の臓器や器官へ移動し、そこに付着して増殖を始める。
(がんのすべてがわかる本P37より引用)
がん細胞が成長して非常に大きくなったとしても、がん細胞が原発部位にとどまっているなら、手術でその部分を取り除けばがんが完治する可能性はありますが、がん細胞があらゆる場所に転移してしまうと、全てのがん細胞を外科療法で除去し切ることは非常に難しくなります。
また重要な臓器に転移してしまうと、その臓器の従来担っている役割が果たせなくなり、やがて患者様を死に至らしめることになります。
宿主が亡くなると自ずとがん細胞も消滅するので、転移に関しても明らかではありません。
これらの背景を知っていると、医学の最大の課題の一つとして、転移を止める方法を見つけることが挙げられるのも納得がいきます。
ここで、がんの『転移』について詳しくみていきましょう。
転移は、肺、脳、骨といいちょうに様々な部位で起こる可能性があります。
原発から転移したがん病変を、転移した部位によって、前の部位を参考にすると、肺転移、脳転移、骨転移等と呼び、これらは病気がその部分に広がっていることを示しています。
また、がん細胞は、肝臓や脳、骨といった血液の流れが豊富な部位やリンパの流れが集まる場所であるリンパ節に転移することが多いとされています。
大腸がん治癒切除後のステージ別再発率
| ステージ | がんの状態 | 3年までの発生率 | 5年までの発生率 | 5年以降の再発率 | 全再発率 |
| 1 | がんが大腸壁にとどまるもの | 2.60% | 3.60% | 0.15% | 3.70% |
| 2 | がんが大腸壁を超えているが、隣接臓器におよんでいないもの | 10.30% | 12.40% | 0.94% | 13.30% |
| 3 | リンパ節転移のあるもの | 26.80% | 30.10% | 0.67% | 30.80% |
(フォント好きが内緒にしたい必須フォント集P.60表7より作成)
上記の表はステージⅠ~Ⅲの大腸がんにおいて、目に見える範囲のがんに対して、全摘手術を行った方を対象に、3年、5年経過後のステージ別再発率を表したものです。表からもわかるように、再発の殆どが、術後5年以内に起こっています。
がんの中には、例えば乳がんのように、再発までの期間が5年以上にわたる可能性が高く、経過を長く見なければならないがんもありますが、多くのがんは手術を受けてから最低5年間は、定期的に検査を受ける必要があるとされています。
その意味でも、5年生存率のデータは再発の可能性を推測する一つの手がかりになると考えています。
肝臓がんの5年生存率
| ステージ | がんの状態 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 1 | 直径2cm以下、1個 | 91.30% | 91.30% | 85.70% | 79.60% | 77.10% | 60% |
| 2 | 直径2cm以下、複数または直径2cm以上、1個 | 95.00% | 87.00% | 81.60% | 76.00% | 67.80% | 315% |
| 3 | 直径2cm以上、複数 | 89.80% | 82.30% | 73.80% | 56.10% | 47.90% | 151% |
| 4 | 広い区域に複数 | 77.90% | 55.70% | 41.40% | 33.40% | 24.50% | 166% |
| 5 | ― | 89.40% | 79.00% | 70.80% | 61.60% | 53.80% | 692% |
(国立がんセンター中央病院1990~2000年症例)
上記は肝臓がんのステージⅠ~Ⅳにおける生存率ですが、これはあくまで生存か否かのデータなので、純粋に再発のみを考えた際のデータでは、少し数値の変動がみられるでしょう。
ここでは肝臓がんを例に挙げて説明しましたが、生存率はステージだけでなく、がんの種類によっても大きな差があります。
胃がん、乳がん、肺がん、膵臓がんそれぞれの、ステージⅡの5年生存率を挙げると、胃がんでは80.9%、乳がんでは78.6%と7~8割であるのに対し、肺がんでは46.4%、膵臓がんでは55.6%と低くなっており、がんの種類によっては再発しやすいがんとそうでないがんがあるということです。
また、おなじがんで同じステージであっても、できた場所やがんの性質などによって再発リスクは変動します。
そして何より、患者様自身の個人差(健康状態)関係していると考えられます。
これらのデータが全てではありませんが、判断材料の一つにはなるでしょう。
がんの主な転移先
がんは種類ごとに転移する臓器がほぼ決まっています。がんの主な転移(浸潤)先は以下のようになります。
肺がん:肺(反対側の肺や同じ肺内で浸潤)・肝臓・脳・骨
乳がん:肺・肝臓・脳(肺を経由して)・骨
胃がん:腹膜・肝臓・近くの臓器へ浸潤(結腸・膵臓など)
大腸がん:肺・肝臓・近くの臓器への浸潤(膀胱・膣など)・脳(肺を経由して)
肝臓がん:肺転移しやすい部位の一つに肺が挙げられますが、その背景には、他の臓器に生じたがん細胞が、血液の流れに乗って肺に到達し、酸素を取り込むために張り巡らされた毛細血管に引っかかることで肺転移が引き起こされると言われています。
がんの『転移』には、種類があり、以下の通りです。
(以下の『転移』は非連続的な広がりです。)
血行性転移
血行性転移とは、原発巣にいたがん細胞が、血液の流れの中に入って全身の他の部分に移ることによって引き起こされる転移です。
この場合、抗がん剤が有効であるケースが多い傾向にあることも特徴です。
抗がん剤の殆どは水溶性なので、血液中を移動するがん細胞には非常に効果があると言われています。
一般的に静脈に乗って転移するので、大腸がんの場合は肝臓への転移が多く、また腎がんでは肺に転移することが多いのはその為です。
リンパ行性転移
リンパ行性転移とは、原発巣のがん細胞が、周囲のリンパ管に入り込み、リンパの流れに乗って移動し、近くのリンパ節から遠くのリンパ節まで広がることによって引き起こされる転移です。
厄介ながんの転移は、殆どの場合、このリンパ行性転移であると言われています。
リンパ管とは、免疫の機能がある場所なので、普通は異物が侵入しても即座に退治されてしまう筈なのに対して、がん細胞はその免疫の機能を持つT細胞等の攻撃を掻い潜って、転移したということになります。
また、抗がん剤は殆どが水溶性なので、大部分が脂で構成されているリンパ管には効きにくいということからも厄介な転移とされる理由の一つです。
播種性転移
まず、内臓と腹膜、胸膜の間には、腹腔や胸膜という隙間があります。
播種性転移とは、この隙間に、近くに出来た臓器にあるがんが増殖して、その内面に種を蒔くように広がっていくのが播種性転移です。(「播種」とは、がんのできた臓器からがん細胞がはがれ落ち、近接する体内の空間(胸腔や腹腔)に分散して拡がることを指します。)
播種性転移は、胃がんや肺がん等でよく見られる転移で、厄介な転移とされています。
胃がんの場合、大きくなったがん細胞が胃壁を突き破って、腹膜に広がっていく「腹膜播種」というがんになることもあります。
また肺がんの場合、胸膜を破って胸膜の表面にがん細胞が散らばる「胸膜播種」というがんになることもあります。
更に、播種性転移には、シュニッツラー転移(ダグラス窩への転移 )、クルーケンブルグ腫瘍(胃がんから卵巣への転移 )といったものもみられます。
また、転移と似た言葉に「浸潤」があります。
浸潤とは、水が染み込んでいくようにがんがその周囲の組織に入り込んでいくことを指し、原発巣から隣接する他の臓器に広がっていくので、転移の一つであるとも考えられます。
このがんはがんの輪郭が分かりにくいので、外科療法等で全てのがんを除去しきるのが難しいという特徴があります。
また、すい臓がんなどで、近くの十二指腸や胆のう、肝臓などへの浸潤は恐ろしい転移で、滅多に治らないとされています。
簡単にまとめると、周囲に攻め込むのが浸潤、遠くまで移動するのが転移です。
また、浸潤の際には、ステージ4(一般的に進行がん)と言われる状態であることが多いとされています。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧