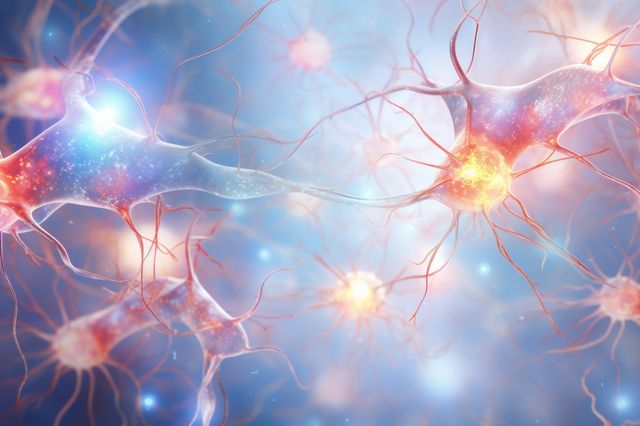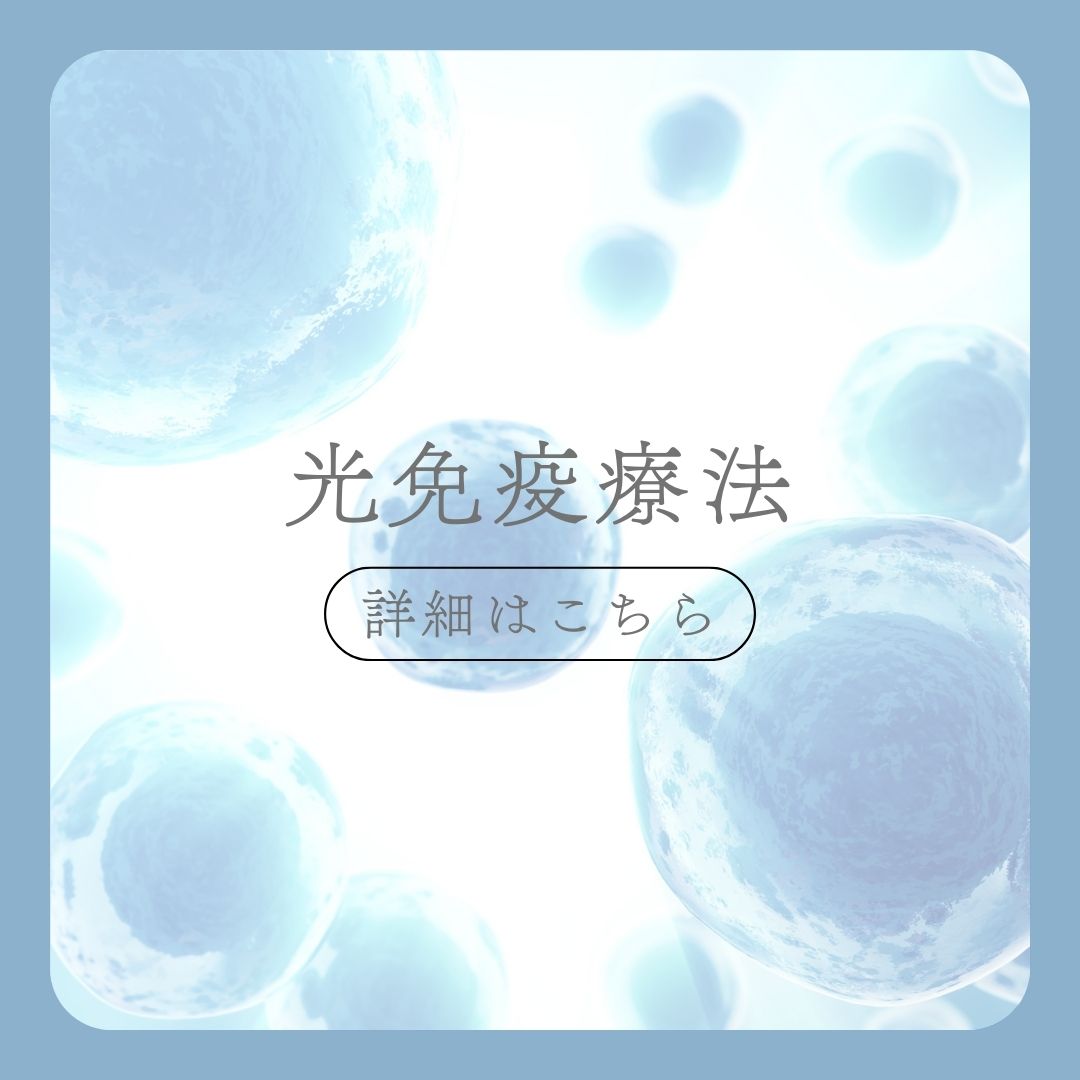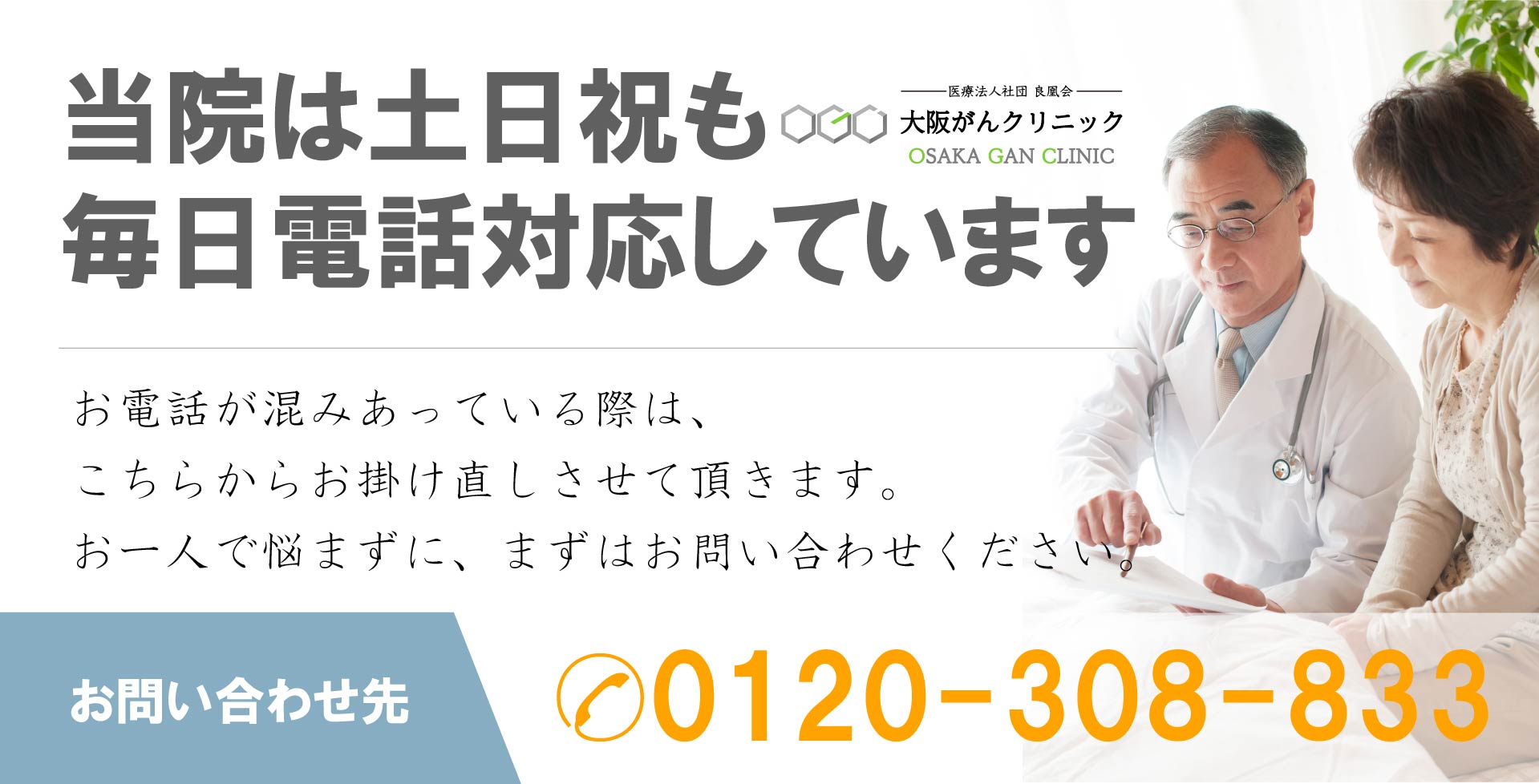卵巣がんの再発転移に関する詳細な解説
卵巣がんは再発転移をしやすいタイプのがんであり、手術や化学療法を行った後、肉眼や画像診断によって確認できるがんが消えたとしても、半数以上が再発・転移するといわれています。
再発・転移する期間は、初回治療終了後から2年以内が多く、ステージⅢやⅣの進行がんでは、2年以内に約55%、5年以内には70%以上が再発するというデータがあります。
そのため、初回治療終了後2年以内は、1~3ヵ月に1回の経過観察(検査)を行う必要があります。
また、がんの再発とは、治療により肉眼や画像診断で確認できる大きさのがんが無くなった後、再びがんが現れることです。
転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って他の臓器に移動し、そこで広がることです。
この記事では、卵巣がんの再発転移について説明し、光免疫療法という治療選択肢についても紹介します。
卵巣がんの発症と進行
卵巣がんは、初期段階では症状が少ないため、半数以上が発見時には進行がんとなっています。
進行した際に出やすい代表的な症状としては、腹部の膨満感や排尿障害、下腹部の痛みなどが挙げられます。
また、卵巣がんが進行すると、これらの症状だけでなく体重減少や食欲不振といった全身症状も現れることがあります。
進行がんの場合、治療後の再発転移のリスクが高まります。
予後が悪い卵巣がんの再発
卵巣がんは、初回治療で根治できたように見えることが多いですが、半数以上は再発してしまいます。
再発転移は、がん細胞が血液やリンパ液を介して体の他の部位に広がることで起こり、特に腹膜や肺、肝臓などへの転移が多いです。
また、再発転移した状態になると、治療の目的は根治を目指すことから症状の緩和や延命に変わり、がんと付き合うことになります。
再発後の生存期間の中央値は約2年といわれており、再発後の予後は悪いことが分かります。
再発後は化学療法が中心
卵巣がんが再発した場合は、化学療法を中心に治療を行います。
しかし、初回化学療法よりも持続期間が短くなることも多く、副作用も強い傾向にあります。
再発した際に使用する薬剤は、初回治療後から再発するまでの期間によって異なります。
初回の化学療法によりがんが無くなってから6ヵ月未満で再発した場合、初回治療とは異なる薬剤を使用します。
6ヵ月以上経ってから再発した場合、初回治療で使用したプラチナ製剤を含めた多剤併用療法(複数の薬剤を同時に投与)が行われます。
また、腫瘍の摘出が可能と考えられる症例では、腫瘍減量術(手術)が有効な場合もありますが、適応は慎重に考慮されます。
その他にも、放射線療法は症状の緩和を主な目的として行われることがあります。
化学療法で出る副作用
前述したように、再発後の化学療法では、初回化学療法より副作用が強く出る傾向にあります。
化学療法で出る副作用としては、抗がん剤の点滴中か24時間以内に、吐き気やアレルギー反応、1~2週間後に白血球や血小板の減少、倦怠感などがあります。
また、2~4週間後以降に脱毛や手足の痺れ、味覚障害などが出ることもあります。
副作用が出た時は、我慢せずに病院へ連絡してください。
光免疫療法の原理と効果
光免疫療法は、特定の薬剤と光を組み合わせてがん細胞を攻撃する治療法です。
薬剤はがん細胞に集積され、その後特定の波長の光を照射することで、がん細胞を破壊します。
この方法は、卵巣がんの再発転移に対しても適応できる可能性があります。
光免疫療法は、他の治療法と組み合わせることで、相乗効果が期待出来ます。
以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。
まとめと今後の展望
卵巣がんの再発転移は、診断でがんが見えなくなったとしても半数以上の症例で起きている。
再発後の生存期間の中央値は約2年であり、一般的ながんより予後が悪い。
再発転移の主な治療法は化学療法ですが、初回化学療法より効果の持続期間が短く、副作用も強い傾向にある。
光免疫療法は、卵巣がんの再発転移にも適応できる可能性がある。
早期の診断と適切な治療が、再発転移のリスクを低減する鍵となります。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧