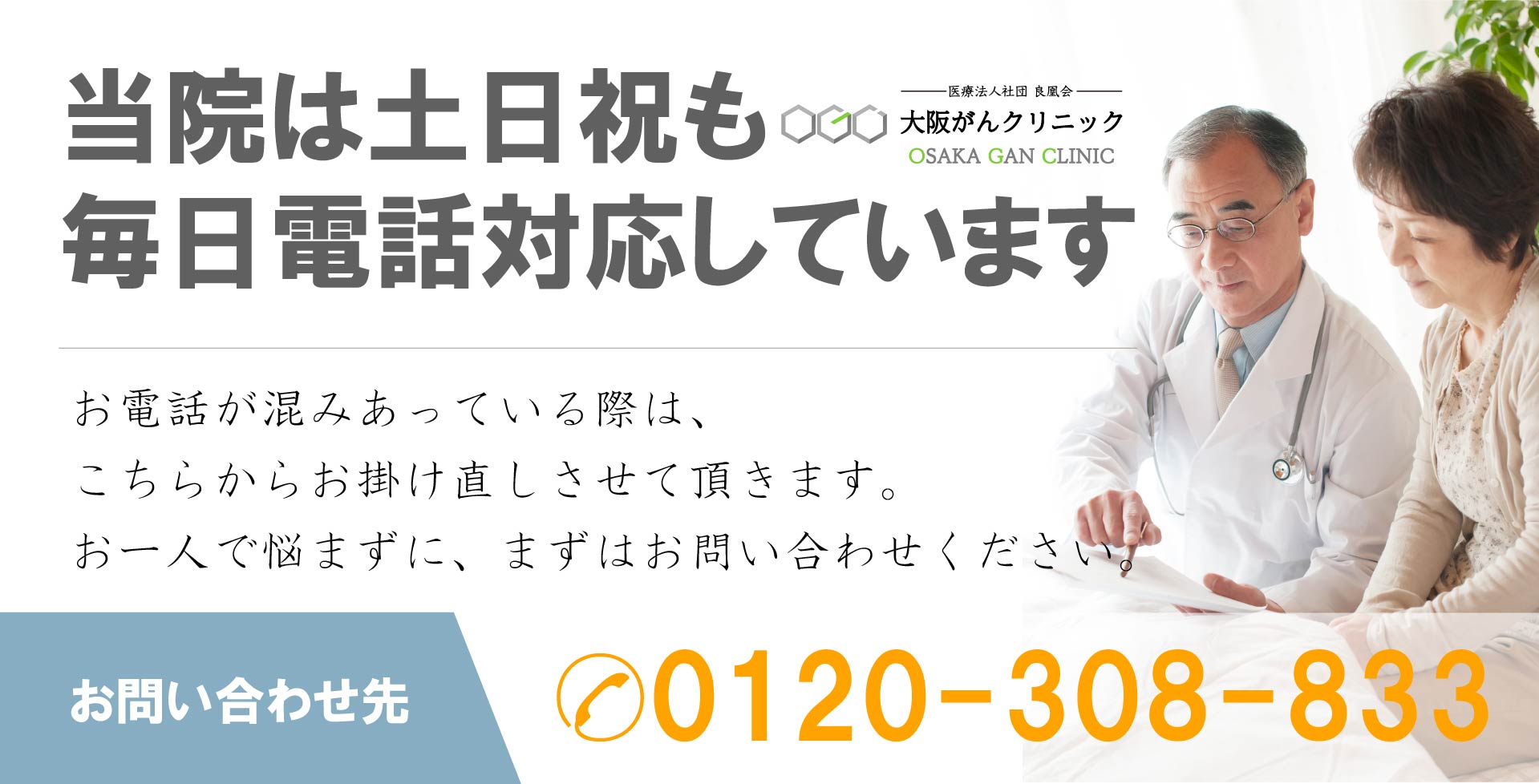乳がんの検診についての詳細解説
乳がんとは
乳がんは、乳腺組織に発生するがんを指します。
乳腺組織は、乳房の中に存在し、乳汁を生産する役割を持っています。
乳がんは、この乳腺組織の細胞が異常に増殖することで発生します。
乳がんは、女性のがんの中で最も発症率が高いとされています。
早期に発見し、適切な治療を行うことで、予後が大きく改善される可能性があります。
乳がんの検診の重要性
乳がんの初期段階では、自覚症状がほとんど現れないことが多いです。
そのため、自分では気づかない間に進行してしまうことがあります。
定期的な検診を受けることで、早期に異常をキャッチし、早期治療を受けることができます。
早期発見・早期治療は、乳がんの治療成功率を大きく向上させる鍵となります。
また、早期に発見することで、乳房を温存する治療や、より軽度な治療を選択することが可能となります。
乳がん検診の詳細な方法
乳がんの検診には、以下のような方法が主に用いられます。
| 検診方法 | 説明 |
|---|---|
| 触診 | 医師や看護師が手で乳房を触り、しこりや変化を確認します。乳房の外側から内側、上から下へと丁寧に触診を行います。 |
| マンモグラフィ | X線を使用して乳房の内部を詳しく調べる方法です。特に中高年の方に有効とされています。 |
| 超音波検査 | 高周波の音波を利用して乳房の内部を映像化します。特に若い方や、乳腺組織が密な方に有効とされています。 |
| MRI検査 | 磁気を使用して乳房の詳しい画像を取得します。高リスク群の方や、他の検査で明確な結果が得られなかった場合に推奨されることがあります。 |
検診結果とその後の対応
乳がん検診で異常が検出された場合、さらに詳しい検査や診断が必要となります。
細胞の採取や生検を行い、がん細胞の有無やタイプを確認します。
診断結果に基づき、専門医と相談し、最適な治療法を選択します。
治療方法には、手術、放射線治療、薬剤治療などがあります。
治療の選択や進行には、患者様の意向も大切にされます。
まとめと今後の対応
乳がんの検診は、早期発見・早期治療のために非常に重要です。
乳がんに関する知識を持ち、自分の健康を守るための一歩として、検診を受けることを強くおすすめします。
また、検診結果に不安や疑問がある場合は、専門医に相談することが大切です。
乳がんは、早期発見すれば治療の成功率が高まるため、定期的な検診を続けることが大切です。
健康を守るために、自分自身の体を大切にし、適切な検診を受けることを心がけましょう。

【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次
がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。
医療法人社団良凰会 医師一覧